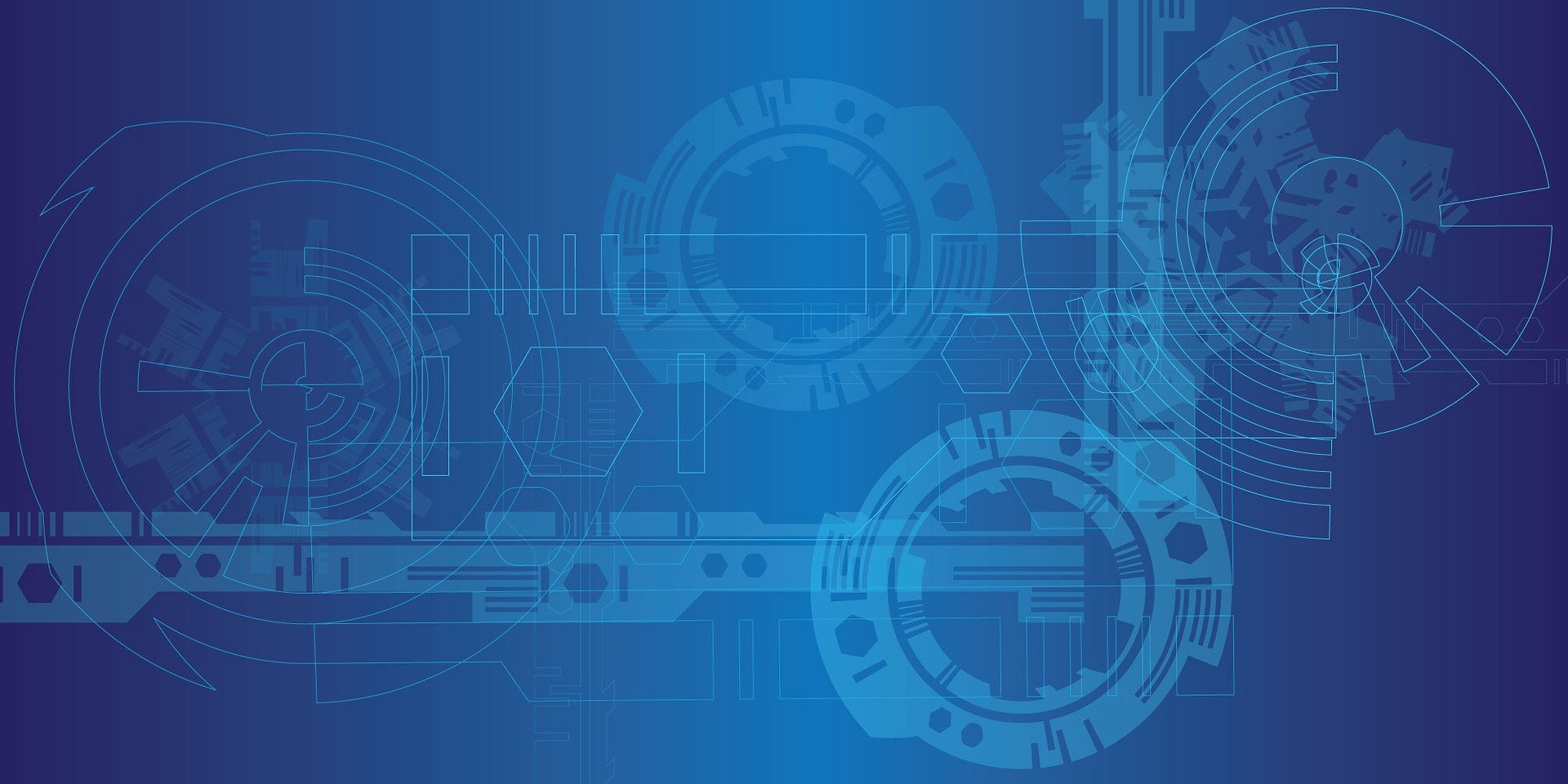※本記事の内容は、2025年11月10日時点の情報に基づいたものです。
※記事中の画像は、生成AIを用いて作成しています。
前々回の記事にも登場した、「ローカルベンチマーク」。
通称「ロカベン」。
補助金の申請書などで見かけたことのある方も多いかもしれませんが、実はこれは単なる“書類”ではありません。
ロカベンは、企業の現状を多面的に「見える化」し、経営者と金融機関・支援機関が共通の言語で対話するためのツールです。
今回は、その内容と活用のポイントをご紹介します。
ロカベンとは?──企業の「健康診断」ツール

ローカルベンチマーク(略称:ロカベン)は、経済産業省が公開している企業の健康診断ツールです。
業績数値などの財務情報(数値面)だけでなく、事業内容や組織体制といった非財務情報(定性面)も含めて企業を多面的に把握し、強みと課題を浮き彫りにすることを目的としています。
このツール(Excelワークブック)は、経済産業省のサイトから無料でダウンロードすることができ、
- 自社の現状を整理したいとき
- 金融機関・支援機関と共通理解をつくりたいとき
- 補助金や認定申請で経営計画をまとめたいとき
など、様々な場面で幅広く活用されています。
財務の視点と非財務の視点──数字の「結果」と「原因」をつなぐ

ロカベンは、
- 財務面(6つの指標)
- 非財務面(商流・業務フロー)
- 非財務面(4つの視点)
の3枚のシートで構成されています。
1. 財務の6指標:経営の“結果”を読み解く
ロカベンの財務分析シートには、企業の健康状態を多面的に見るための6つの指標が並びます。
| 指標 | 何を意味するか? | 読み解くポイント |
|---|---|---|
| 売上増加率 | 成長性 | 単年の数値だけでなく、トレンドを重視する |
| 営業利益率 | 本業の収益力 | 原価・値付け・販路を見直す |
| 労働生産性 | 1人が生み出す利益 | 働き方・人材育成との関係を見る |
| EBITDA有利子負債倍率 | 財務の健全性 | 設備投資や借入の妥当性を確認する |
| 営業運転資本回転期間 | 資金効率 | 回収・在庫・支払のバランスを見る |
| 自己資本比率 | 安定性 | 信用・調達力と直結 |
これらはいずれも単なるスコアではなく、「なぜこの数値になっているのか」を掘り下げる出発点です。
業種・規模別の基準値と比較できる点も特徴で、単純な“良し悪し”ではなく同業比較での位置づけを理解することができます。
2. 非財務の視点:数字の“原因”を探る
一方、非財務視点の2つの分析シートでは、財務指標の背景となる要因を可視化します。
以下①~③の3つの領域からなり、財務の結果(たとえば利益率低下)を「なぜそうなったのか」という原因側から探っていく仕組みです。
受注〜生産〜出荷〜アフターまでの流れ。
どこでムダやロスが発生しているかを把握します。
顧客構成・販路・競合・市場シェアなどを分析し、どこに強み・リスク・機会があるかを明確化します。
■経営者(理念・方針・後継者など)
将来目標の明確さや、経営改善に向けた意思の強さを評価します。
「承継や外部支援の必要性」の判断に直結します。
■事業(商品・市場・差別化など)
収益性や成長性の源泉を明確化します。
営業戦略・開発方針に活かすことができます。
■環境・関係者(取引先・地域・協力関係など)
商流リスクや社会的価値(地域貢献、雇用維持)を把握します。
サプライチェーン脆弱性の評価は重要です。
■内部管理体制(人事・IT・品質・財務管理など)
業務効率や再現性の担保、拡大時の組織的対応力を確認します。
労働生産性や運転資本の改善策につなげることができます。
これらの情報を財務指標と照らし合わせることで、「営業利益率が低いのは価格設定が原因か、業務設計が原因か」など、原因と結果をつなぐ思考が可能になります。
「自社理解と共通認識形成」からはじめよう

ロカベンは、単に数値を並べて評価するものではありません。
経営者が自社を正しく理解し、金融機関・支援機関と共通の認識を持つための「現状把握ツール」です。
財務・非財務の両面を整理する過程で、自社の強みや課題、そして改善の方向性が見えてきます。
また、その結果を共有することで、関係機関との対話がスムーズになり、より実効的な支援や資金調達につながります。
自社の現状を整理したいとき
「数字」と「実態」を結びつけ、現状を客観的に把握できます。
金融機関・支援機関と共通認識を持ちたいとき
共通のシートをもとに、建設的な対話を進められます。
補助金や認定申請を準備するとき
経営計画の根拠資料として活用でき、加点対象になる場合もあります。
ロカベンは「完成品」ではなく、「出発点」です。
シートを作ることで経営者自身の考えが整理され、数字と実態を結びつけて自社を語れるようになる。
その気づきが、経営改善の第一歩になります。