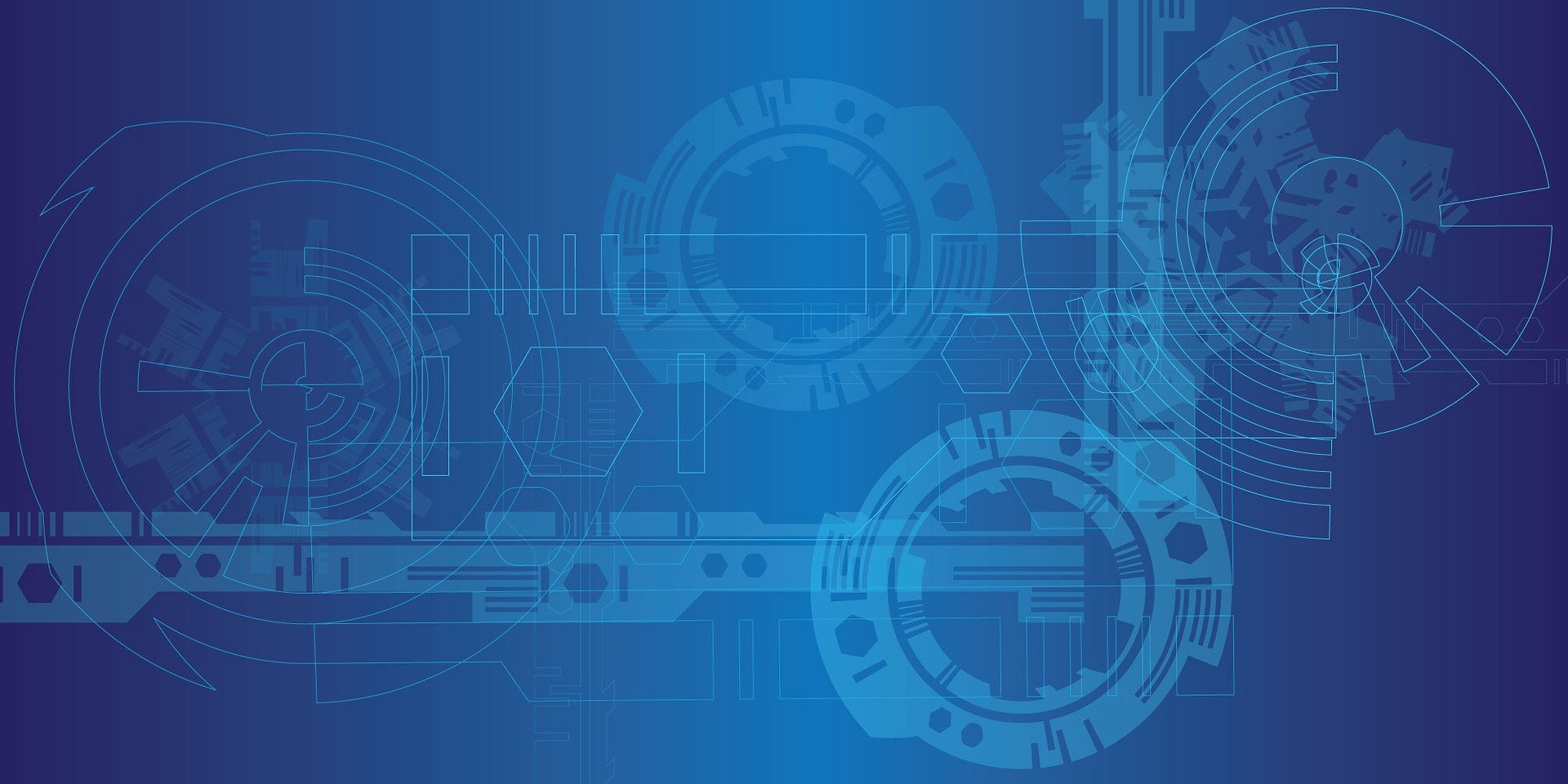※本記事の内容は、2025年10月28日時点の情報に基づいたものです。
※記事中の画像は、生成AIを用いて作成しています。

決算書は税金を計算するためのもの
そう思っていませんか?
この連載「決算書を“読む”社長になる!数字で会社を強くする話」では、決算書を“過去の結果”ではなく“未来の経営判断の材料”として活かすヒントをお伝えします。
本連載は今回が最終回。
締め括りとして、「決算を“見せる”ことで信頼を築く」という視点から、数字の整え方・伝え方について見ていきましょう。
「整った決算」が信頼をつくる


決算書は、税務申告のためだけの書類ではありません。
銀行や取引先にとっては、あなたの会社の「信頼度」を測る最も客観的な資料です。
数字の精度が高く、整った決算は、それだけで経営の誠実さや透明性を示します。
一方で、勘定科目の整理が甘かったり、年によって数字のブレが大きいと、「この会社は管理が甘いのでは?」と見られてしまうこともあります。
つまり、決算を整えること自体が、信頼を積み上げる行為なのです。
伝わる“見せ方”が経営の評価を変える


決算書をどう見せるかで、銀行や取引先の印象は大きく変わります。
たとえば、利益が出ていても、在庫や売掛金が膨らんで資金繰りが厳しい場合、「資金計画を改善中」と説明できる資料を添えることで、前向きな印象を与えられます。
また、赤字決算であっても、



新規事業への先行投資であり、来期黒字化を見込んでいます。
と明確に語れれば、経営の意図が伝わります。
数字そのものだけでなく、数字の背景をどう説明するかが、社外の評価を左右するのです。
経営方針・投資計画・資金繰りの見通しなどを、決算書に沿って一貫して説明できることが、“見せる経営”の第一歩といえます。
“決算を語れる社長”が会社を強くする


信頼される会社に共通するのは、「社長自身が数字を理解している」という点です。
決算書を税理士だけに任せず、自ら読み、語れるようになることで、銀行との関係も変わります。
たとえば、融資相談の場で「営業キャッシュフローは安定しており、返済計画も確実です」と自信をもって話せる社長は、金融機関に安心感を与えます。
さらに、数字をもとに経営方針を説明できるようになると、社内外に「この会社はしっかりしている」という信頼が生まれます。
決算は“信頼を築くツール”。
数字を語る力を磨くことが、会社をより強く、より開かれた存在にしていくのです。
決算を「作る」から「活かす」へ、そして「見せる」へ。
数字の裏にある意図を語れる社長こそ、信頼を集め、次のチャンスを引き寄せます。