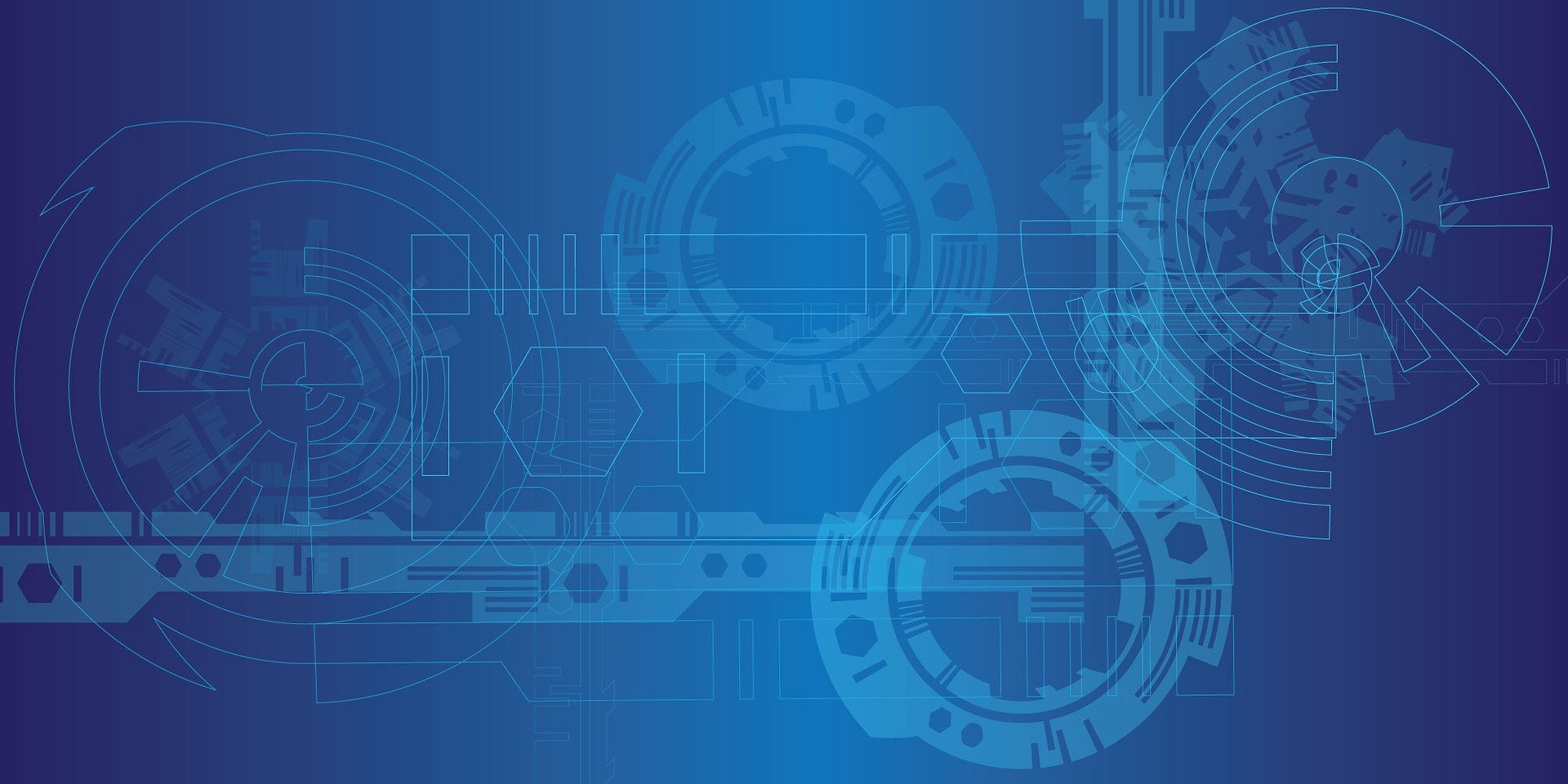※本記事の内容は、2025年10月13日時点の情報に基づいたものです。
※記事中の画像は、生成AIを用いて作成しています。

決算書は税金を計算するためのもの
そう思っていませんか?
この連載「決算書を“読む”社長になる!数字で会社を強くする話」では、決算書を“過去の結果”ではなく“未来の経営判断の材料”として活かすヒントをお伝えします。
第1回目の今回は、決算書を「経営の地図」として捉え直し、社長が数字を読むことの意味について見ていきましょう。
社長が舵を取るための“経営の地図”


決算書は、会社の現状を示す「経営の地図」です。
地図がなければ、目的地にたどり着けないのと同じように、数字を見ずに経営の方向を定めることはできません。
多くの社長が「決算は税理士に任せている」とおっしゃいます。
実際、数字を整えるのは税理士の大切な仕事です。
一方で、その数字をもとに次の一手を考えるのは、社長だからこそできること。
数字を“読む”ことは、会社の現状を理解し、次の一手を考えるための最初のステップです。
決算書を、社長が会社の“現在地”を確かめるための道具として活かしていきましょう。
決算書が語る3つのこと


決算書は、会社の全体像を3つの側面から示します。
- 第一の側面:損益計算書(PL)
会社がどれだけ儲けたかを示す「利益の地図」 - 第二の側面:貸借対照表(BS)
会社にどんな財産と負債があるかを示す「体力の地図」 - 第三の側面:キャッシュフロー計算書(CF)
お金がどこから来て、どこへ行ったかを示す「資金の地図」
この3枚をあわせて読むことで、会社の“今の位置”と“進むべき道”が見えてきます。
決算書は単なる報告書ではなく、会社の現状を映し出す経営のナビゲーションツールなのです。
数字を見れば、経営の判断が明確になる


数字を意識して経営していると、判断の根拠がよりはっきりしてきます。
たとえば、



黒字のはずなのに、なぜか手元にお金が残らないんだよな……。



売上はあるけど、仕入や支払いが先行して資金がきついな。
こうした状況も、損益計算書(PL)だけでなく、貸借対照表(BS)やキャッシュフロー計算書(CF)をあわせて見ることで、原因を正しくつかめるようになるのです。
売上や利益の推移、支出の増減、借入残高の動きなど、数字には会社のコンディションがそのまま表れます。
定期的に数字を振り返ることで、問題が起きる前に手を打てる経営に変わっていきます。
決算書は、社長が“今の会社”を知るための地図です。
数字を通して会社の状態を見つめ直すことが、より良い経営への第一歩となります。
次回は、決算書のうち「損益計算書(PL)」を取り上げ、「儲けの構造」を読み解くポイントをお伝えします。